Keynote で作成したスライドを Speaker Deck にアップロードすると Transcript が文字化けする問題があり、その対処法を以下の記事で紹介していた。
最近のMacはPostScriptをビルトインでサポートしなくなった
しかし、記事の中で言及していたMacの「プレビュー」がPostScriptファイルのサポートをやめてしまったため、現在ではPostScriptからPDFに変換する部分は別のツールを使って行う必要がある。
代わりのツールの一つ:Ghostscript
この記事では、代替の方法のひとつとして、Ghostscriptを紹介する。
Macの場合、Homebrewでインストールするのが簡単だろう。
$ brew install ghostscript
GhostscriptでPostScriptからPDFに変換する
Keynoteから「プリント」→「PostScriptとして保存」として作成したPostScript(ps)ファイルを、Ghostscriptの ps2pdf を使ってPDFに変換することができる。
$ ps2pdf input.ps output.pdf
こうして作成したPDFをSpeaker Deckにアップロードすれば、文字化けを回避することができる。
補足
手元の環境で作成したpsファイルでは、 ps2pdf では以下のようにエラーになり変換できなかった。
$ ps2pdf input.ps output.pdf GPL Ghostscript 10.03.0: PDFDocEncoding ad is undefined
@toshimaru_eさんの手元では ps2pdf でも変換ができているようなので、ファイル側に問題があるように思われる。
自分の手元だと ps2pdf で問題なく動作しました! pic.twitter.com/K7iq5JEJFZ
— toshimaru (@toshimaru_e) March 9, 2024
なお、原因は特定できていないのだが、同じファイルもPDF 1.3を用いる ps2pdf13 を使えば変換することができた。
$ ps2pdf13 input.ps output.pdf
謝辞
以前書いた記事の方法が現在では一部使えなくなっていること、Ghostscriptで代替できることを指摘してくださり、 ps2pdf での動作の状況も教えていただいた@toshimaru_eさんに感謝します。
speakerdeckのTranscript文字化け問題困っていたけどこの方法で治った。ただ Preview App がPostScriptに対応しなくなったので、brewで入るghostscriptが必要 » Keynote で作成したスライドを Speaker Deck にアップロードすると Transcript が文字化けする問題への対処法 https://t.co/Zv0P5fp5yt
— toshimaru (@toshimaru_e) March 9, 2024
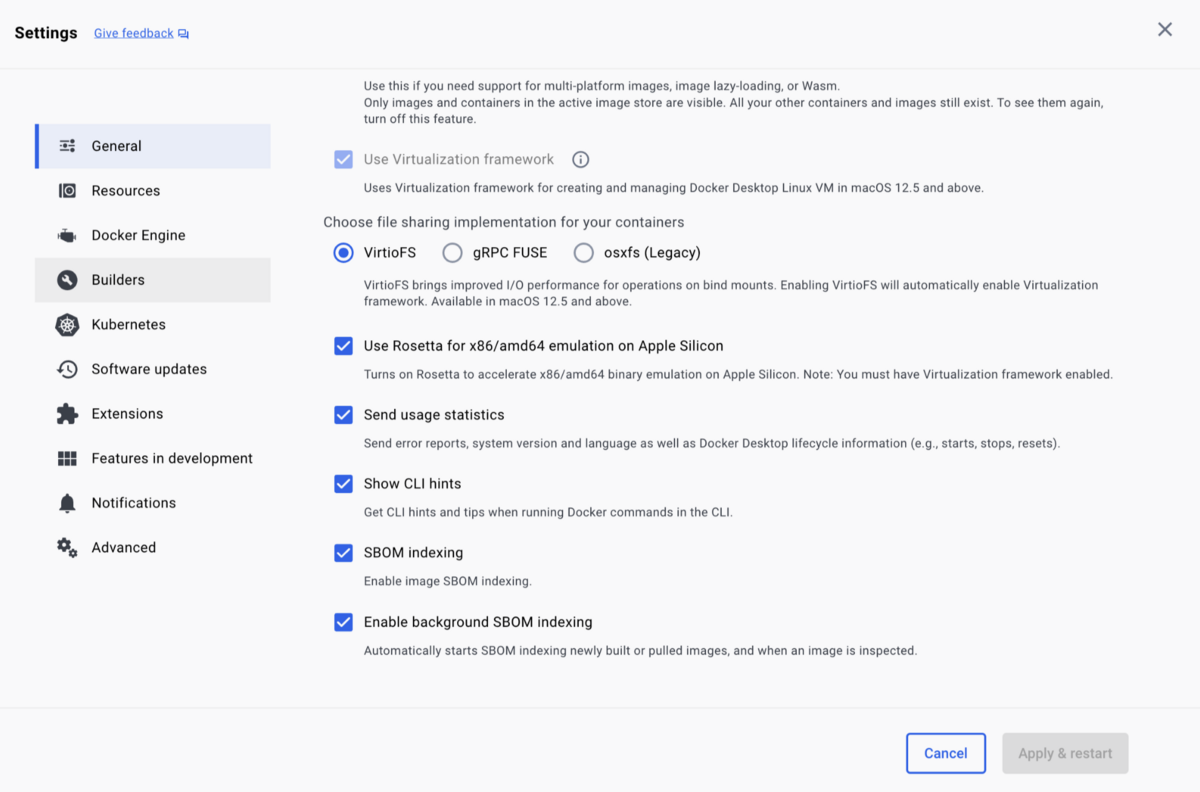










![石原夏織 5th Anniversary Live -bouquet- Blu-ray【特装版】(特典なし) [Blu-ray] 石原夏織 5th Anniversary Live -bouquet- Blu-ray【特装版】(特典なし) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41nK4EjQIoL._SL500_.jpg)

